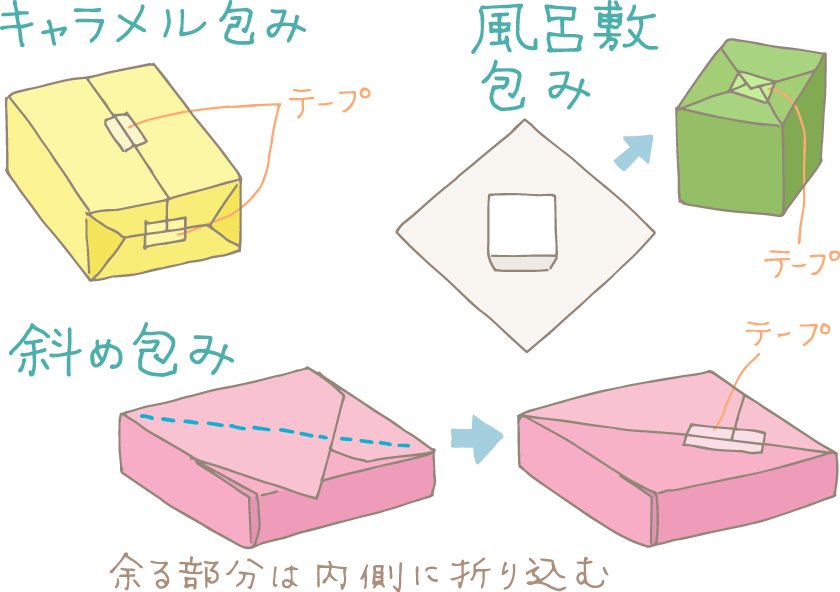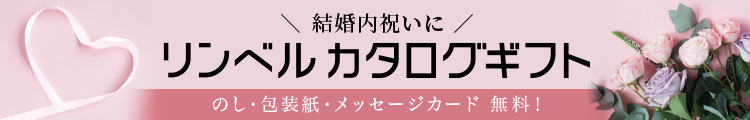婚姻届や住民票などで手続きをする際に「世帯主」という項目を目にしたことがある方も多いでしょう。「世帯主=主たる生計維持者」というイメージが先行しがちですが、実際には15歳以上であれば、同一世帯の誰が世帯主になっても差し支えないのが一般的です。それでは、どのような基準で世帯主を決めればよいのでしょうか?
今回は、結婚後の世帯主の決め方についてわかりやすく解説します。
世帯主とは?
まず、「世帯」とは「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、もしくは独立して生計を営む単身者」のことをいいます。単独世帯・核家族世帯(夫婦・夫婦と未婚の子・ひとり親と未婚の子)・三世代世帯などがあります。
そして、「世帯主」とは「年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者」のことをいいます。年齢に関わらないとされるものの、行政上の手続きにおいては15歳以上でなければ世帯主にはなれないのが一般的です。
世帯主の役割
選挙の投票所入場券が、世帯主に宛てて世帯全員分配送されてきたり、国からの給付金が、世帯主の銀行口座に世帯全員分振り込まれたりしたという覚えはないでしょうか。このように、行政上の手続きにおいては、世帯員個々人ではなく、世帯主が代表して連絡を受けることになっています。
世帯主の行政上の義務
世帯主に代表で連絡がいく例として「国民健康保険税や国民年金のお知らせが、世帯主に宛てて加入者全員分配送されてくる」こともあります。これは行政手続き上、世帯主にその世帯の加入者の国民健康保険税の納税義務や国民年金の納付義務などが課せられているからです。
つまり「会社員で社会保険・厚生年金に加入している世帯主の夫に宛てて、自営業の妻の国民保健・国民年金のお知らせが届く」といったケースも考えられます。
世帯主になるメリット・デメリット
世帯主のメリット
企業が従業員に支給する「住宅手当」や「家族手当」を受けられる可能性があります。支給要件などは企業によって定められているためケースバイケースですが、「従業員本人が世帯主である」ことを要件に含むのが一般的です。
これに加えて「主たる生計維持者である」ことを要件とするなど、いわゆる“二重取り”を認めないケースがほとんどですから、手当の多寡で安易に世帯主を決めたり、夫と妻両方の勤務先から手当を受け取ろうと世帯分離を試みたりするようなことはやめましょう。そもそも、夫婦については原則的に世帯をわけることはできないとされています。
世帯主のデメリット
先述した通り、世帯主は社会的な手続きや税金の支払いなどを世帯の代表として担うことになります。これをデメリットと見なすかは判断がわかれますが、相応の責任や負担が生じることは確かです。
世帯主の決め方・ポイント
収入が安定している方を世帯主にするとよいでしょう
世帯全員の納税義務が課されるのは世帯主です。世帯主の収入から納税すると考えた場合、収入が安定している世帯員が世帯主になるほうがスムーズでしょう。例えば共働きの会社員であれば、それぞれの待遇や将来的な昇進・昇給の見込みも踏まえて、どちらの収入が安定しそうか話し合ってみましょう。
福利厚生が整っている方を世帯主にする
先述した通り、住宅手当などの福利厚生が整っている方を世帯主にすれば、家計の負担を減らすことができます。例えば、どちらかが専業主婦(主夫)となる場合や、自営業を営むといった場合こうした福利厚生はありません。1つの選択肢として、会社員として勤める方が世帯主になる方向で調整してもよいでしょう。
世帯主は一家でいちばん頼りになる人がいいみたいだね
元々住んでいた方を世帯主にする
「夫婦のどちらかが元々住んでいた家で、結婚を機に同居を始める」といった場合、賃貸契約の変更などといった諸手続きを避けるために、元々住んでいた方が世帯主になる場合もあります。
同棲の場合は?
婚姻届の提出を伴わないいわゆる「同棲」の場合、次のようなケースがみられます。
- 同じ住所へ住民票を移して世帯をわけ、それぞれが世帯主になる。
- 同じ住所へ住民票を移して1人が世帯主になり、もう1人は「夫または妻(未届)」、「同居人」とする。
- 1人だけが住民票を移し、世帯主となる。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、一般的には比較的制約が少なく、同棲解消もスムーズな「それぞれが世帯主となる」ケースが多いようです。
世帯主は2人でも問題ない?
親夫婦・子夫婦が同居している住宅を「二世帯住宅」などと呼ぶことがあります。このように親などと同居している場合、同棲と同じように同じ住所でも親(夫婦)・子(夫婦)で世帯をわけ、それぞれが世帯主を立てる「世帯分離」ができます。また逆に、1つの世帯として全員をまとめる世帯主を立てることもできます。ただし、世帯主は世帯の代表ですので、1つの世帯の世帯主として2人以上を立てることはできません。「世帯分離」や「世帯合併」を希望する場合は、世帯変更届と本人確認書類をお住まいの市区町村の役所に提出する必要があります。
また、インターネットなどで「世帯合併 ◯◯区」でお住いの市区町村を入力して検索してみると、自治体によっては申請書などがダウンロードできます。役所に行く前に一度検索してみることをおすすめします。
世帯主を決めたら結婚前後の準備も進めよう
結婚前後は夫婦の姓や世帯主を決定するだけでなく、住民票の変更や各種行政手続き、姓が変わる方は銀行口座やクレジットカードの名義変更、引越す方は各種サービスの住所変更など、やるべきことがたくさんあります。その中でも、結婚祝いをいただいた方への「結婚内祝い」は、無事結婚できたことのご報告と、祝福への感謝の気持ちを伝える大切なマナーのひとつです。
きちんと感謝の気持ちを伝えるのも世帯主の役目だね
結婚祝いのお返しも準備しておこう!
「結婚内祝い」は、俗に「結婚祝いのお返し」などとも呼ばれますが、本来「内祝い」自体にお返しの意味はありません。「内祝い」はお祝いしてくださった方へ、慶びごとをおすそわけするといった意味合いの贈り物なのです。
もちろん、ただ返せばいいというものではありません。忙しい結婚前後の時期ではありますが、お祝いしてくださった方の気持ちにお応えするべく、結婚式や入籍の1ヶ月後までを目途として、あまり遅くならないうちに用意しましょう。
リンベルでは、結婚内祝いに好適なギフトを多数取り揃えています。結婚内祝いの贈り方について、よくあるご質問などもまとめて確認できますので、ぜひチェックしてみてください。