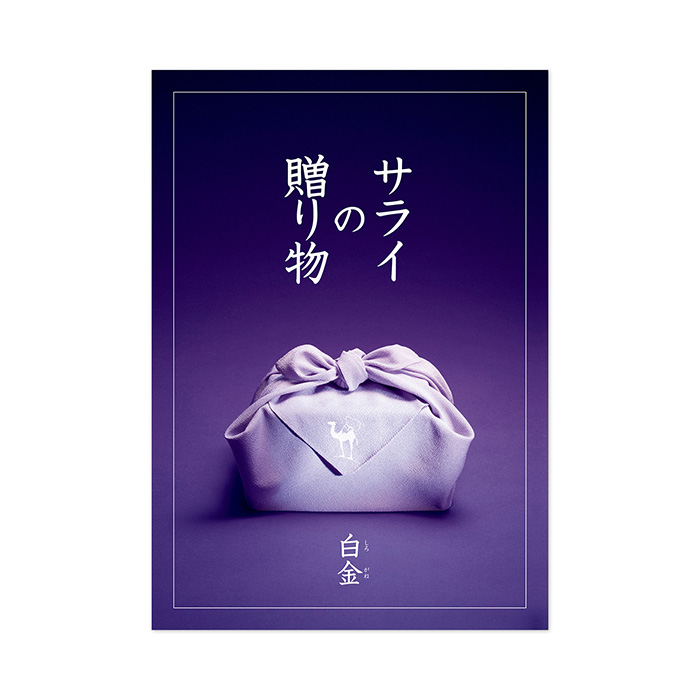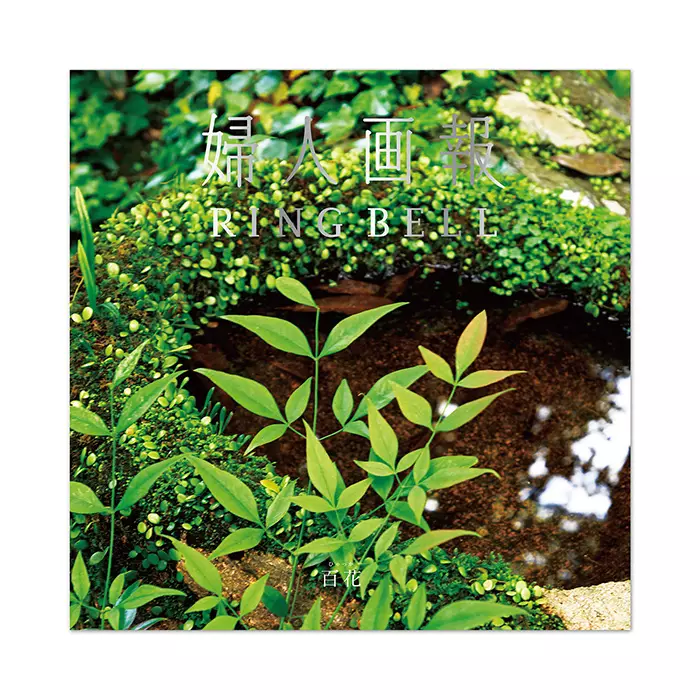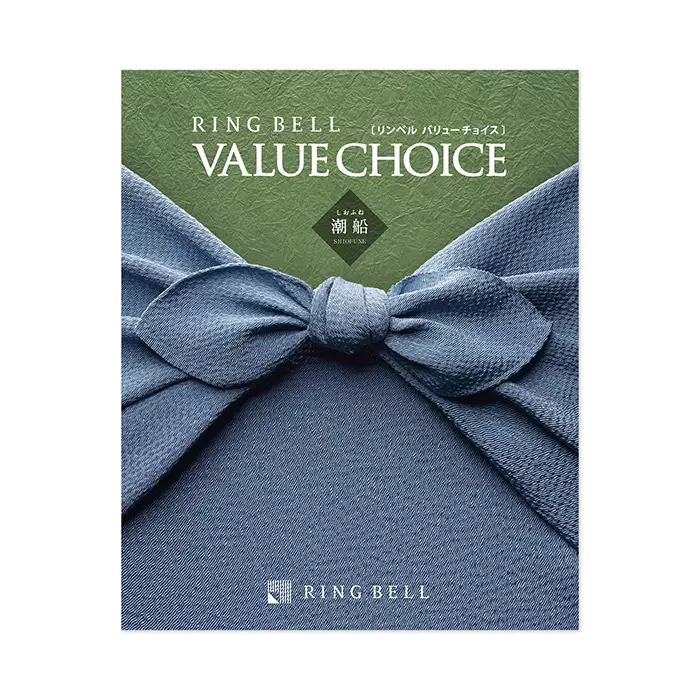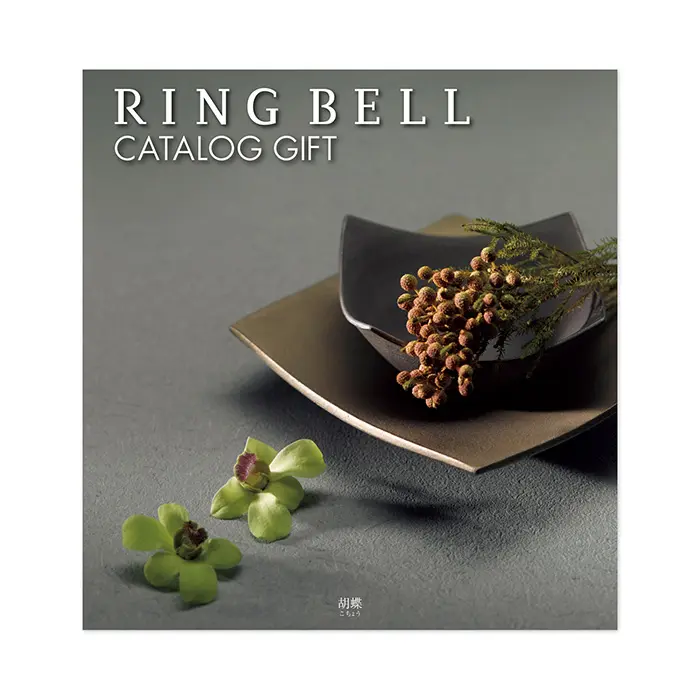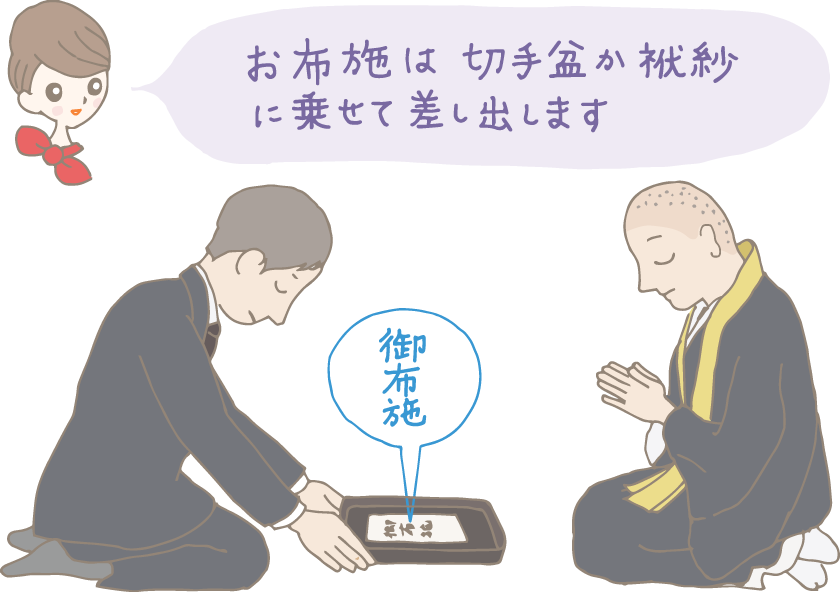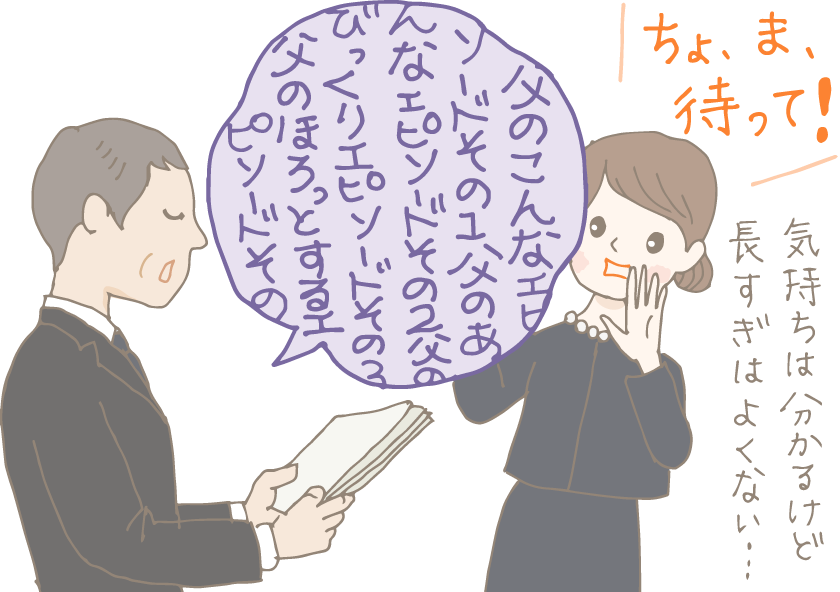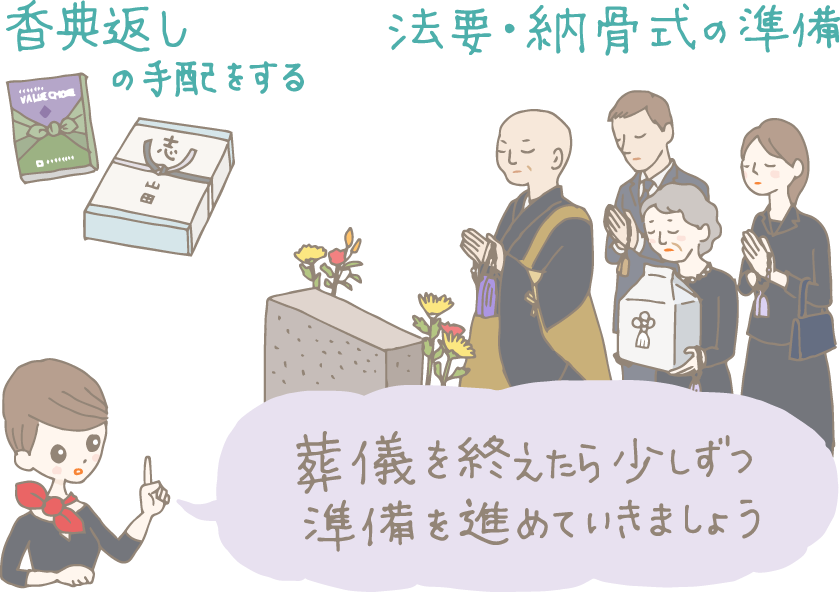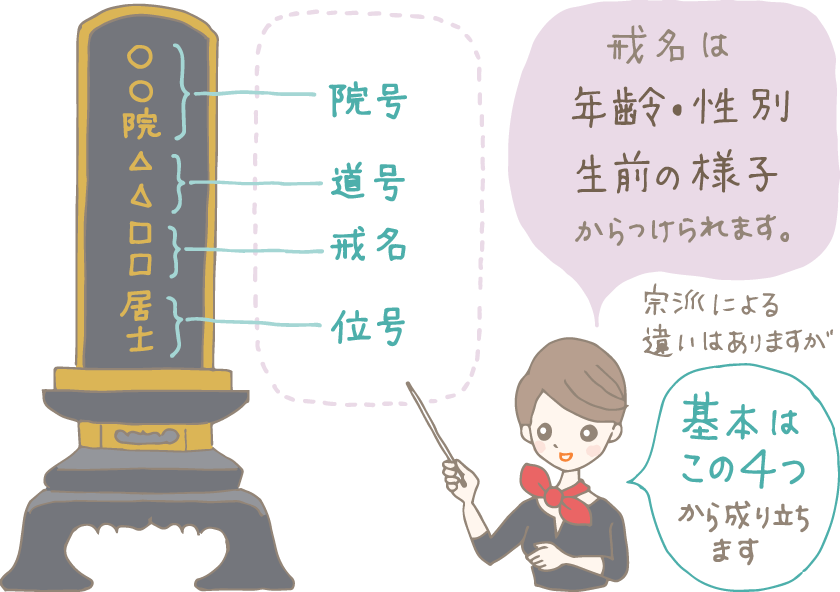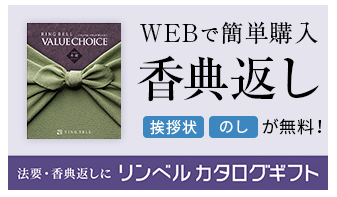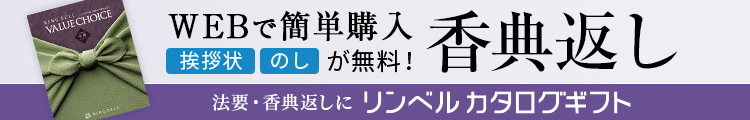「志」は一般的な表書き
香典返しの表書きは宗教や地域によって異なります。仏式では一般的に「志」と書き、家名を添えます。「志」には「気持ち」という意味があり、気持ちばかりのお返しという意思を表しています。関西から西日本では「満中陰志」とすることもあり、これは「満ちる」「中陰(故人の四十九日間)」「志」を合わせて「四十九日の忌明けに贈る遺族からの感謝のしるし」を意味します。
神式では「偲び草(偲草)」、キリスト教では「記念品」と表書きするのが一般的です。いずれの場合も、地域の慣習に合わせることが大切です。
「志」と表書きする掛け紙の書き方
掛け紙は黒白、黒銀、または黄白の水引を印刷したものが一般的です。仏式であれば、蓮の絵が印刷されていることも多いようです。
水引の色や蓮の絵の有無は、「葬儀のみ」「四十九日まで」など地域によって違いがありますから、葬祭業者などに確認しておくと安心でしょう。
書き方としては、水引の結び目より上側に「志」、下側に施主の姓(もしくは姓名)を入れます。
表書きの文字の色
表書きは薄墨の筆か筆ペン、またはサインペンで書くのが基本です。関東の一部の地域では、法事のお返しや引出物は濃い墨で書くケースもあります。
薄墨とは薄い墨色に色味を調整したもので、涙で文字がにじむような悲しみを表しているといわれています。
基本的には法事を行う地域の慣習に合わせるようにしましょう。
弔事の際に薄い墨で書くのは、悲しみの涙で墨がにじむ気持ちを表すためだと言われています。ほかにも、悲しみを薄め流したいと言う意味や、墨をする間も惜しんで駆けつけたという説もあるようです。

「志」と「寸志」は1文字で大違い!
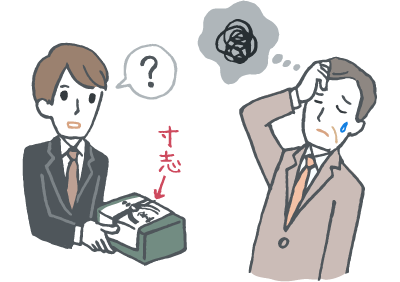
「寸志」は「目上の方が目下の人の方へ渡す『ほんの気持ち』」
お店へ掛け紙を依頼する場合などに注意したいのが「志」と「寸志」の取り違えです。「志」は弔事に使われるのが一般的ですが、「寸志」は目上の方から目下の方へのお礼や差し入れに使われるものです。
字面は似ていますが、読みは「こころざし」と「すんし」で違いますので、口頭でもしっかり確認するようにしましょう。
香典返しにおすすめのお品
香典返しにおすすめのお品は、消耗品や食べ物などの「消え物」がよいとされています。例えば、洗剤や石鹸、お茶、海苔などの乾物、お菓子などが一般的です。最近では、お渡しする方が好きな商品を選べる「カタログギフト」も金額に応じて分けてお渡しできるため重宝されています。
「掛け紙」と「のし」は別物?
掛け紙とは、弔事に用いられる包装紙であり、水引のみが印刷されたものです。「のし」が印刷されていないことが特徴です。
一方、のし紙とは、水引と一緒に「のし」(薄く伸ばした鮑を模したもの)も印刷されている紙のことを指します。
のしはお祝い事全般に用いられるものなので、シーンによって使い分けが必要です。